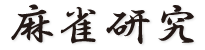麻雀とは?
麻雀のルールでは、これから麻雀をはじめようと思っている方や麻雀をはじめたばかりの方向けのコンテンツになります。
まずは麻雀がどんなゲームなのかを簡単に説明します。
プレー人数
麻雀は4人でプレーするゲームです。(3人でプレーする三麻と呼ばれるゲームもありますが、当サイトでは一般的な4人麻雀について解説します。)
ゲームの目的
34種類、合計136枚の牌に描かれた図柄と数字を組み合わせてアガリと呼ばれる牌の組み合わせをつくります。
アガリをつくると点数がもらえ、揃えるのが難しい組みわせほど点数が高くなります。4人のプレーヤーでアガリをつくりあって点数を競うゲームです。
勝敗
いずれかのプレーヤーがアガリを完成させるまでを1局とよびます。誰もアガリを完成させることができなければ流局となり、そのゲームが終了します。1回のゲームでは1人のプレーヤーが親と呼ばれるゲームを開始するプレーヤーを2回やるとすべてのゲームが終了します。
ゲームが終了した時点で最も多くの点数を持っているプレーヤーの勝ちとなります。
すごくざっくり言うと点取りゲームです。レアな役を作ったほうが得点が多く貰え、最終的に一番点数を持っていた人が勝ちになります。
麻雀牌の種類
麻雀牌の種類を見てみましょう。まだ無理に牌の名前は覚える必要はないので参考程度にご覧ください。
麻雀牌は34種類、合計136枚
麻雀で使う牌は大きく数牌(シューパイ)と字牌(ツーパイ)に分かれます。
数牌(シューパイ)
萬子(マンズ)、筒子(ピンズ)、索子(ソーズ)の3種類があり、それぞれ1~9までの数字があります。
萬子(マンズ)
イーワン |
リャンワン |
サンワン |
スーワン |
ウーワン |
ローワン |
チーワン |
パーワン |
キューワン (チューワン) |
筒子(ピンズ)
イーピン |
リャンピン |
サンピン |
スーピン |
ウーピン |
ローピン |
チーピン |
パーピン |
キューピン (チューピン) |
索子(ソーズ)
イーソー |
リャンソー |
サンソー |
スーソー |
ウーソー |
ローソー |
チーソー |
パーソー |
キューソー (チューソー) |
字牌(ツーパイ)
風牌(フォンパイ/カゼハイ)
トン |
ナン |
シャー |
ペー |
※麻雀では東西南北といわず東南西北と呼ぶのが一般的です。
三元牌(サンゲンパイ)
ハク |
ハツ |
チュン |
※三元牌の正式名称はそれぞれ白板(パイパン)・緑發(リューファ)・紅中(ホンチュン/フォンチュン)という。
麻雀牌の分類
麻雀牌をカテゴリーごとに分けると以下の図のようになります。
| 数牌 | 2~8牌 | 中張牌 | |
| 1・9牌 | ヤオチュー牌 | ||
| 字牌 | 風牌 | ||
| 三元牌 |
数牌の1と9牌のことを老頭牌(ロートーハイ)と呼び、 2~8の牌を中張牌(チュンチャンハイ)と呼びます。三元牌、風牌、老頭牌を合わせてヤオチュー牌と呼びます。
牌の分類を覚えておくとアガリ役が覚えやすくなります。例えば三元牌を使ってつくる大三元や老頭牌を使ってつくる混老頭(ホンロウトウ)などがあります。
麻雀をプレイしていれば自然と牌の名前は覚えるのでここで無理に覚える必要はありません。
13枚でアガリの形をつくる
麻雀では最初に13枚(親は14枚)の牌を持ってプレイします。そこからアガリの形を作っていきます。
配牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ゲームを始める前に牌山から自分の持ち牌(手牌)を持ってきます。これを「配牌(ハイパイ)」と呼びます。配牌される牌の数は親は14枚、子は13枚です。
理牌(リーハイ)
| 同じ種類の数牌を数字順に並べる | 字牌をまとめる |
配牌が終わった後の手牌はバラバラの状態で見づらいので、図柄や数字ごとに並び替えを行います。これを「理牌(リーハイ)」と呼びます。
並べ方のルールは特に決まっていませんが、見やすいように数牌は同じ種類の数字順に、字牌は同じ種類の字牌でまとめておくとわかりやすいです。
アガリの形にする
| アタマ (雀頭) |
メンツ1 | メンツ2 | メンツ3 | メンツ4 |
理牌したあとは1つのアタマ+4つのメンツの形をつくっていきます。
アガルためにはアガリ役が必要になります。アガリ役とは決められた牌の組み合わせの形をつくるものです。
アタマとメンツを揃える
アガルためには1つのアタマ+4つのメンツが必要になります。
2枚で1組の雀頭(アタマ)と、3枚で1組の面子(メンツ)を4つを揃え、合計14枚でアガリの形を構成します。
雀頭(ジャントウ)
アタマは正式には雀頭(ジャントウ)と言います。同じ牌2枚で構成しますが、使用する牌は数牌、字牌のどちらでも構いません。
数牌の雀頭の例
![]()
![]()
![]()
![]()
字牌の雀頭の例
![]()
![]()
![]()
![]()
面子(メンツ)
面子(メンツ)は3枚で1セットで構成します。面子には順子(シュンツ)と刻子(コーツ)の2種類があります。
順子(シュンツ)
同じ種類の数牌で連続した3つの数字をつくる。
○順子の例
マンズの順子
![]()
![]()
![]()
ピンズの順子
![]()
![]()
![]()
ソーズの順子
![]()
![]()
![]()
×ダメな例
同じ種類の数牌でなければならない
![]()
![]()
![]()
9から1にはつながらない
![]()
![]()
![]()
字牌ではダメ
![]()
![]()
![]()
刻子(コーツ)
数牌、字牌どちらでもよく、同じ図柄3枚で構成する。
○刻子の例
数牌の刻子
![]()
![]()
![]()
風牌の刻子
![]()
![]()
![]()
三元牌の刻子
![]()
![]()
![]()
×ダメな例
同じ種類の数牌でなければならない
![]()
![]()
![]()
同じ種類の字牌でなければならない
![]()
![]()
![]()
塔子(ターツ)
あと1枚で順子になる2枚
| |
|
|
順子になる |
順子になる |
順子になる |
対子(トイツ)
あと1枚で刻子になる2枚
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ポイント
まずは、アガルためには1つのアタマ+4つのメンツが必要ということを覚えましょう。
アタマは同じ牌2枚で構成され、メンツは順子(シュンツ)と呼ばれる3つの数字の並びか、刻子(コーツ)と呼ばれる同じ牌3つで構成されています。
牌を1枚とって1枚捨てる
牌山から牌を1枚取ることをツモといい、いらない牌を1枚捨てることを捨て牌と呼びます。麻雀はツモと捨て牌を繰り返してアガリを目指します。
ツモって捨てる実践例
牌山から![]() をツモってきました。
をツモってきました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ
↓
アガリ役をつくる上で![]()
![]()
![]() が不要です。 まずは
が不要です。 まずは![]() を捨てることにします。
を捨てることにします。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 捨て牌
捨て牌
↓
続いて次のツモでは![]() をツモりましたが、不要なのでそのまま捨てます。
をツモりましたが、不要なのでそのまま捨てます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ・捨て牌
ツモ・捨て牌
捨て牌は並べる
捨て牌は麻雀卓の中央部分に1列が6枚ずつになるように並べて捨てます。麻雀牌を捨てる部分を河(ホー)と呼びます。一般的にはカワと呼ばれることが多いです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
あがるための条件
あがるためには「雀頭+4つの面子」の形をつくりますが、それだけではあがることができません。
麻雀ではあがるためには”アガリ役”が必要になります。
アガリ役がなければあがれない
アガリ役とは図柄の組み合わせの条件によって成立するアガリの形です。アガリ役は全部で36種類あり、アガリ役によって点数が決まっています。
アガリの形になっているが役がない例
| └ チー ┘ | ツモ |
上図はチーをしてしまっているためアガリ役が何もなくツモってもアガれない例です。チーについては後ほど解説するので、ここではアガれない場合があることだけ覚えてください。
1飜縛り(イーファンしばり)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ
前述通り麻雀ではあがるために役が必要です。これを1飜(イーファン)しばりと呼びます。アガリ役がないのにアガリを宣言するとチョンボと言ってペナルティを受けてしまいます。
上図の例だと平和(ピンフ)と門前清自摸和(メンゼンツモ)という2つの役でアガることができます。
テンパイの待ちの形
手牌にあと1枚加わるとあがれる状態を聴牌(テンパイ)といい、 アガリになる牌をアガリ牌や待ち牌と呼びます。
聴牌(テンパイ)とは?
聴牌(テンパイ)とはあと1枚でアガリの形になる状態のことです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() か
か![]() がくるとアガリ!
がくるとアガリ!
上図のようにあと1枚でアガれる状態がテンパイになります。
待ちの形
牌の待ち方によって、リャンメン待ち、カンチャン待ち、ペンチャン待ち、シャンポン待ち、タンキ待ちの5つに分類されます。
両面(リャンメン)待ち
連続した数牌の両側を待つ。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() か
か![]() がくるとアガリ!
がくるとアガリ!
この場合![]() がくれば
がくれば![]()
![]()
![]() のメンツができ、
のメンツができ、![]() がくれば
がくれば![]()
![]()
![]() のメンツができアガることができます。
のメンツができアガることができます。
嵌張(カンチャン)待ち
数を飛ばして連続した2枚の数牌の真ん中の牌を待つ。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() がくるとアガリ!
がくるとアガリ!
この場合![]() がくれば
がくれば![]()
![]()
![]() のメンツができアガることができます。
のメンツができアガることができます。
辺張(ペンチャン)待ち
数牌の1・2の牌か、8・9の牌を持っていて3か7を待つ。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() がくるとアガリ!
がくるとアガリ!
この場合![]() がくれば
がくれば![]()
![]()
![]() のメンツができアガることができます。
のメンツができアガることができます。
シャンポン待ち(シャボ待ち)
2つの対子で待ち、どちらかが雀頭になる。よくシャボ待ちと呼ばれています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() か
か![]() がくるとアガリ!
がくるとアガリ!
この場合![]() がくれば
がくれば![]()
![]()
![]() のメンツができ、
のメンツができ、![]() がくれば
がくれば![]()
![]()
![]() のメンツができアガることができます。
のメンツができアガることができます。
単騎(タンキ)待ち
雀頭にする牌の片方を待つ。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() がくるとアガリ!
がくるとアガリ!
この場合![]() がくれば
がくれば![]()
![]() の雀頭ができアガることができます。
の雀頭ができアガることができます。
ポン
ポンは他のプレイヤーの捨て牌を1枚もらって刻子(コーツ)をつくるものです。
ポンをするための条件
あと1枚で刻子になる牌を2枚持っていることが条件です。
左隣(上家)、正面(対面)、右隣(下家)のいずれのプレイヤーの捨てた牌でもポンできます。
ポンの手順
- 自分の欲しい牌をほかのプレイヤーが捨てたら「ポン」と声を出す。
- ポンをしたい2枚の牌を倒し、ほかのプレイヤーに見せる。
- ポンをした牌を自分のところに持ってきて、卓上の右端に図柄の面を上にして置く。
- 自分の手牌からいらない牌を1枚捨てる。
ポンをした牌の置き方
ポンをした牌を卓上の右端に置くときは、ポンをした牌を捨てた人の場所にあわせて牌を横に向けて置きます。
左隣(上家)からポンした場合
![]()
![]()
![]() 左端の牌を横に倒す
左端の牌を横に倒す
正面(対面)からポンした場合
![]()
![]()
![]() 真ん中の牌を横に倒す
真ん中の牌を横に倒す
右隣(下家)からポンした場合
![]()
![]()
![]() 右端の牌を横に倒す
右端の牌を横に倒す
ポンをしたあと
ポンをしたプレイヤーは牌を捨てたらツモをせずに、ポンをしたプレイヤーの右隣のプレイヤー(下家)にツモの順番が移動します。
チー
チーは他のプレイヤーの捨て牌を1枚もらって順子(シュンツ)をつくるものです。
チーをするための条件
あと1枚で順子になる牌を2枚持っていることが条件です。チーは左隣(上家)のプレイヤーの捨てた牌からしかできません。
チーの手順
- 自分の欲しい牌を左隣のプレイヤー(上家)が捨てたら「チー」と声を出す。
- チーをしたい2枚の牌を倒し、ほかのプレイヤーに見せる。
- チーをした牌を自分のところに持ってきて、卓上の右端に図柄の面を上にして置く。
- 自分の手牌からいらない牌を1枚捨てる。
チーをした牌の置き方
チーをした牌を卓上の右端に置くときは、数字の順番や牌の入る場所に関係なく必ずチーをした牌を横向きにして左側に置きます。
リャンメン(両面)をチーした場合
![]()
![]()
![]() 左端の牌を横に倒す
左端の牌を横に倒す
カンチャン(嵌張)をチーした場合
![]()
![]()
![]() 左端の牌を横に倒す
左端の牌を横に倒す
ペンチャン(辺張)をチーした場合
![]()
![]()
![]() 左端の牌を横に倒す
左端の牌を横に倒す
チーをしたあと
チーをしたプレイヤーは牌を捨てたらツモをせずにチーをしたプレイヤーの右隣のプレイヤー(下家)にツモの順番が移動します。
カン
カンとは同じ図柄の牌を4枚揃え、同じ図柄の牌3枚と同様に1つの面子(メンツ)として扱うものです。
カンをするための条件
同じ図柄の牌が4枚揃うことを槓子(カンツ)と呼びます。カンツを確定するために行うのがカンです。面子は基本的に3枚で1組ですが、同じ図柄の牌4枚を1つの面子として使用できます。また、カンには3つの種類があります。
暗槓(アンカン)
手牌の中に同じ図柄の牌が4枚ありこれをカンツにすることを暗槓といいます。なお、ほかのプレイヤーの牌を使わないので食ったことになりません。
大明槓(ダイミンカン)
手牌の中に同じ図柄の牌が3枚(コーツ)があり、ほかのプレイヤーの捨て牌を使ってつくるものです。
小明槓(ショウミンカン)・加槓(カカン)
自分がポンをした牌と同じ牌をツモった際、ポンしたコーツをカンツにすることです。
暗槓(アンカン)の手順
- 手牌の中に同じ図柄の牌が4枚そろったら「カン」と声を出す。
- カンをしたい4枚の牌を他のプレイヤーに見せる。
- リンシャン牌をツモっていらない牌を捨てる。
- 牌の真ん中2つを裏にして右端に置く。
暗槓した場合の牌の置き方
![]()
![]()
![]()
![]()
真ん中の2つの牌を裏向きにして右端に置く。
大明槓(ダイミンカン)の手順
- 自分のほしい牌を他のプレイヤーが捨てたら「カン」と声を出す。
- カンをしたい3枚の牌(コーツ)を他のプレイヤーに見せる。
- カンした牌を自分のところに持ってきて、卓上の右端に図柄の面を上にして置く。
- リンシャン牌をツモって、いらない牌を捨てる。
左隣(上家)のプレイヤーから大明槓した場合の置き方
![]()
![]()
![]()
![]()
一番左の牌を横にして置く。
向かい(対面)のプレイヤーから大明槓した場合の置き方
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
真ん中の牌のどちらかを横にして置く。
右隣(下家)のプレイヤーから大明槓した場合の置き方
![]()
![]()
![]()
![]()
一番右の牌を横にして置く。
加槓(小明槓)の手順
- すでに自分がポンをしている牌の4枚目をツモったら「カン」と声を出す。
- ポンをしてある牌の横に倒した牌の上にカンをした牌を置く。
- リンシャン牌をツモって、いらない牌を捨てる。
左隣(上家)のプレイヤーから加槓した場合の置き方

一番左の牌を横に重ねて置く。
向かい(対面)のプレイヤーから加槓した場合の置き方

真ん中の牌の重ねて横にして置く。
右隣(下家)のプレイヤーから加槓した場合の置き方

一番右の牌を横に重ねて置く。
カンをした後
カンをしたプレイヤーは手牌が1枚足りないのでリンシャン牌をツモって、いらない牌を捨てる必要があります。なお、ツモの順番はカンをして牌を捨てた人の右隣(下家)に移ります。
アガリ方は2種類ある
アガリ方には「ツモ」と「ロン」の2種類あります。もし誰もアガることが出来なければ「流局」になります。
ツモ
自分で牌山からツモってきて、そのツモした牌でアガることを「ツモアガリ」と呼びます。得点はツモアガリしたプレイヤー以外の3人で分けて支払います。
- 待っていたあがり牌をツモる。
- 「ツモ」と声を出す。
- ツモったアガリ牌を自分の手牌から離して置き、手牌を倒して他の3人のプレイヤーに見せる。
ロン
他のプレイヤーが捨てた牌でアガることを「ロンアガリ」と呼びます。
得点はアガリ牌を捨てた人が1人で支払います。
- 他のプレイヤーが自分のアガリ牌を捨てる。
- 「ロン」と声を出す。
- 手牌を倒して他の3人のプレイヤーに見せる。
流局
牌山に牌を14枚残して、誰もアガることが出来ない時は「流局」と言って、その局が終了します。流局をした際、親がテンパイしていない場合は次のプレイヤーに親が移ります。
ツモとロンのまとめ
| アガリ方 | 点数 | |
| ツモ | 自分でツモってきてアガる | 他のプレイヤー(3人)で分けて支払う |
| ロン | 他人の捨てた牌でアガる | アガリ牌を捨てた人が1人で支払う |
ロンされた場合は1人で点数をすべて支払わなければならないため、なるべくロンされないように注意する必要があります。
ここまでが麻雀の基本的なルールになります。繰り返し読むことによって麻雀のルールが身につくと思います。それでは、長文にお付き合いいただきありがとうございました。
麻雀のルールだけでは解説しきれなかった基礎の部分は基本編で解説しているのでぜひこちらもご覧ください。