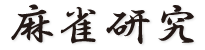ゲームの流れ
今回は麻雀のゲームの流れを解説します。
半荘戦(ハンチャンセン)と東風戦(トンプウセン)
麻雀は半荘(ハンチャン)もしくは東風(トンプウ)という単位でプレイされます。
半荘は大きく分けて東場(トンバ)と南場(ナンバ)で構成されています。わかりやすく言うと、前半と後半と言った感じになります。
東場と南場はそれぞれ4回の局(キョク)という単位で争われます。
半荘戦の流れ
| ▼ | 東場 |
| ├ | 東一局(トンイッキョク)/東発(トンパツ) |
| ├ | 東二局(トンニキョク) |
| ├ | 東三局(トンサンキョク) |
| └ | 東四局(トンヨンキョク)/東ラス |
| ▼ | 南場 |
| ├ | 南一局(ナンイッキョク) |
| ├ | 南二局(ナンニキョク) |
| ├ | 南三局(ナンサンキョク)/ラス前 |
| └ | 南四局(ナンヨンキョク)/オーラス |
半荘戦全体を見るとこのような流れになります。
最終の南四局のことをオーラスと呼びます。また、東一局を東発、東四局を東ラス、オーラス直前の南三局をラス前と呼ぶことがあります。
局は、子がアガるか親が連荘条件を満たしていない場合、流局になり次の局へと流れていきます。
親がアガるか、親が連荘条件を満たしている場合は、次の局へと進まずに一本場、二本場、三本場・・・というように同じ局が再び続きます。例えば、東一局で親がアガった場合、東二局に進まずに、東一局一本場となります。
東風戦
続いて東風戦を見てみましょう。東風戦は半荘戦の東場のみを行う試合単位です。
| ▼ | 東場 |
| ├ | 東一局(トンイッキョク)/東発 |
| ├ | 東二局(トンニキョク) |
| ├ | 東三局(トンサンキョク)/ラス前 |
| └ | 東四局(トンヨンキョク)/オーラス |
東場のみしか行わないため単純に半荘戦の半分ぐらいの時間で試合を終わらせることができます。最近は短時間で決着がつけられることからネット麻雀などでメジャーになってきました。
立直(リーチ)
麻雀役は最低1飜ないと完成になりません。「3枚1組のグループが4つ+1枚1組の雀頭」という形にして、最低でも1飜の役を組み込むことでアガることができます。
今回はもっとも基本的な役であるリーチ(立直)について解説しますが、まずはアガれない場合を見てみましょう。
ロンあがりできない例
まずはロンあがりできない例を見てみましょう。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
上図のような手牌だった場合アガリ牌は![]() と
と![]() になるというのはわかるかと思います。
になるというのはわかるかと思います。
この場合、ツモあがりをすれば門前自摸の1飜がついてアガることができるのですが、逆に言うとツモらなければ役が何もないのでアガることができません。
このようにツモあがりはできるけど、ロンあがりできない場合があります。このような状態を解消するのにはどうしたらよいでしょうか。実はこの状況でも1飜の役をつけることができるのです。
リーチ
アガリの直前の状態をテンパイ(聴牌)といいます。
このテンパイ状態になったことを相手に教えることがリーチです。リーチをかけると1飜の役がつきます。
リーチをかけることにより1飜の役がつくため「1飜ないとアガれない」という条件をクリアしたことになり、役がない状態でもアガることができるようになります。
リーチの条件
リーチはいつでも好きなときにかけられるわけではありません。
ポンやチーをしていない状態でテンパイかつ、持ち点が1,000点以上ある場合のみリーチをかけることができます。
この1,000点は供託といってリーチをかける際に支払うもので、簡単に言うと「リーチ料金」みたいなものになります。アガることができれば1,000点は返ってきますが、アガれなかった場合は返ってきません。
まとめ
リーチの条件をまとめました。
- 門前(ポン、チー、カンをしていない)状態であること。
- アガリの1つ前の状態(テンパイ)になったらできる。
- 自分の持ち点が1,000点以上ないとできない。
- リーチをすると1飜の役がつく。
フリテン(振聴)
フリテンは重要なルールでよく初心者が困惑する部分なので、3種類あるフリテンを1つずつ順番に解説していきます。
麻雀の大原則
麻雀はツモしては捨ててを繰り返して最終的にアガリを目指すのですが、自分で捨てた牌では絶対にロンアガリできないというルールがあります。
フリテンの例
まずは簡単な例を見てみましょう。
手牌)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自分の手牌が上図のような場合![]() がくればアガリになります。
がくればアガリになります。
しかし、自分の捨て牌が![]()
![]()
![]()
![]()
![]() だった場合、当たり牌である
だった場合、当たり牌である![]() を一度捨ててしまっているため、ロンあがりすることができません。ちなみにこの場合ツモなら問題なくアガることができます。
を一度捨ててしまっているため、ロンあがりすることができません。ちなみにこの場合ツモなら問題なくアガることができます。
この原則を逆に考えると相手の捨てた牌(現物)では絶対にロンされないということになります。
リャンメン待ちの例
続いてよく出てくるリャンメン待ちでのフリテンの例です。
手牌)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この場合、![]() と
と![]() がくればアガリになります。
がくればアガリになります。
自分の捨て牌が、![]()
![]()
![]()
![]()
![]() だった場合、先ほどと同じフリテンの考え方で
だった場合、先ほどと同じフリテンの考え方で![]() ではロンあがりできないのはわかるかと思います。
ではロンあがりできないのはわかるかと思います。
しかしこの場合、![]() だけでなく
だけでなく![]() でもロンあがりできません。
でもロンあがりできません。
なぜかというと、数種類ある待ち牌の中の1つでも捨ててしまっていたら、残りの1種類の牌でもロンはできないのです。つまり、自分の捨てた牌+自分の捨てた牌を含んだ待ち牌全てでロンあがりできないということになります。
同順フリテン
前項で解説したのが第一のフリテンというべき「フリテン」です。今回は第二のフリテンと呼ばれる「同順のフリテン」を解説します。
同順内で発生するフリテン
まずは例を見てみましょう。
手牌)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
上図のような状態でテンパイした場合は当たり牌は![]() と
と![]() になります。
になります。
この状況で下家(自分から見て右手のプレイヤー)が![]() を捨てます。これでアガることができるのですが、あえてロンしなかっとします。
を捨てます。これでアガることができるのですが、あえてロンしなかっとします。
あえてロンしない場合はいくつかあり、例えばロンした相手が1,000点しか持っていなくて、ロンするとゲーム終了になる場合はあえてロンしない場合があります。このように当たり牌が出ているのにロンと言わないのを見逃すといいます。
さて、下家が![]() を捨てて、その次に対面(向かいのプレイヤー)も
を捨てて、その次に対面(向かいのプレイヤー)も![]() を捨てたとします。この場合、対面からロンあがりすることができません。これを同順(同巡)フリテンといいます。
を捨てたとします。この場合、対面からロンあがりすることができません。これを同順(同巡)フリテンといいます。
再び自分の番が回ってきた時点で同順フリテンは解消されるため、再び対面が![]() を捨てた時に今度はロンアガリすることができます。
を捨てた時に今度はロンアガリすることができます。
リーチ後のフリテン
第一のフリテン「フリテン」、第二のフリテン「同順フリテン」ときて、最後に第三のフリテン「リーチ後のフリテン」を解説します。3つも覚えるのは大変ですが、全て第一のフリテンの応用です。
リーチ後に発生するフリテン
第三のフリテンである「リーチ後のフリテン」は割と簡単で、リーチしたら誰かが捨てた当たり牌を一度でも見逃してしまうとロンあがりできなくなるというルールです。
また、リーチ後のフリテンは同順フリテンとは異なり一巡したとしてもアガることはできません。
万が一、リーチをかけて当たり牌を見逃してしまうとツモあがりするしかなくなります。
フリテンのまとめ
第一のフリテン「フリテン」
自分の捨てた牌と、自分の捨てた牌を含む全ての待ちでロンあがりできない。
第二のフリテン「同順フリテン」
1周するまでに当たり牌を見逃すと、自分の順番が来るまでアガれない。
第三のフリテン「リーチ後のフリテン」
リーチ後に当たり牌を見逃すとロンできなくなる。
簡単な点数計算
今まで「飜(ハン/ファン)」を説明してきましたが、1飜で何点ぐらいになるのかを見ていきましょう。
簡単な点数計算表(30符)
| 子の場合 | 飜数 | 親の場合 |
|---|---|---|
| 1,000点 | 1飜(ヒトハン) | 1,500点 |
| 2,000点 | 2飜(フタハン) | 2,900点 |
| 3,900点 | 3飜(サンハン) | 5,800点 |
| 8,000点 | 4,5飜 満貫(マンガン) |
12,000点 |
| 12,000点 | 6,7飜 跳満(ハネマン) |
18,000点 |
| 16,000点 | 8,9,10飜 倍満(バイマン) |
24,000点 |
| 24,000点 | 11,12飜 三倍満(サンバイマン) |
26,000点 |
| 32,000点 | 13飜以上 役満(ヤクマン) |
48,000点 |
点数計算表を見て気付いた人もいると思いますが、「親」は「子」の1.5倍の点数をもらうことができます。
点数のやりとり
ざっくりとした点数がわかったところで、実際の点数のやりとりを解説します。
麻雀のアガリ方は「ツモ」と「ロン」の2種類が存在し、それぞれ支払う点数が異なります。
親がアガった場合
親のツモ
親のツモの場合はシンプルにみんなで3等分します。例えば、親が12,000点アガったら1人4,000点ずつ支払うことになります。
親のロン
親のロンの場合は振り込んだ人(当たり牌を捨てた人)が1人で全ての点数を支払います。例えば、親が12,000点アガったら振り込んだ人は1人で12,000点支払わなければなりません。親にロンされると高い点数を1人で負担しなければならないため、なるべく親には振り込まないようにしたいところです。
子がアガった場合
子のツモ
子がツモった場合は半分を親が支払い、残りを2人の子で2等分します。例えば、8,000点アガった場合、親が4,000点支払い、2人の子がそれぞれ2,000点ずつ支払い、合計で8,000点になります。親は自分がアガった時に高い点数をもらえる分、子がツモあがりした時に多く点数を払わなければなりません。
子のロン
子のロンの場合は親のロンと同様に、振り込んだ人(当たり牌を捨てた人)が1人で全ての点数を支払ます。例えば、8,000点アガったら振り込んだ人は1人で8,000点支払います。
ドラ
今回はドラについて解説します。
アガると1飜がつく
ドラはアガった時に「ドラ牌」を持っているだけで1飜つきます。
ただし、ドラのみで役はつかないので、あくまでボーナス点のようなものとして考えてください。ドラは毎回(毎局)変わるので、牌が配られたらドラが何かを確認するクセをつけましょう。
何がドラなのか
ドラ表示牌といって何がドラなのかを示す牌が雀卓上に置かれており、ドラ表示牌の次の牌がドラになります。
例えばドラ表示牌が![]() だった場合ドラは
だった場合ドラは![]() になります。
になります。![]() の場合は一巡して
の場合は一巡して![]() になります。
になります。
字牌は![]() →
→![]() →
→![]() →
→![]() →
→![]() のようにサイクルしています。ドラ表示牌が
のようにサイクルしています。ドラ表示牌が![]() ならドラは
ならドラは![]() になります。
になります。
三元牌も同様に![]() →
→![]() →
→![]() →
→![]() とサイクルしており、ドラ表示牌が
とサイクルしており、ドラ表示牌が![]() だった場合はドラは
だった場合はドラは![]() になります。
になります。
裏ドラ
リーチをすると通常のドラとは別に裏ドラというものを見ることができます。ドラ表示牌の裏側にある牌が裏ドラの表示牌で、リーチをかけてアガると見ることができます。
裏ドラの表示牌が![]() だった場合、裏ドラは
だった場合、裏ドラは![]() になります。
になります。
赤ドラ
近年、赤ドラと言って![]()
![]()
![]() が混じったゲームも増えています。これもドラと同じ扱いで持っているだけで1飜の扱いになります。通常、ドラは毎回ランダムに変わりますが、赤ドラだけは五萬、五筒、五索に固定されているため「固定ドラ」と考えることができます。
が混じったゲームも増えています。これもドラと同じ扱いで持っているだけで1飜の扱いになります。通常、ドラは毎回ランダムに変わりますが、赤ドラだけは五萬、五筒、五索に固定されているため「固定ドラ」と考えることができます。
また、赤ドラが何枚入っているかはルールによって異なります。
役牌
先ほど紹介したリーチをはじめ、麻雀にはたくさん役があります。今回は登場頻度2位の役牌について解説します。
役牌(飜牌)
全37種ある麻雀役の中でも役牌は登場頻度2位でよく見かける役です。
役牌は字牌の中でも三元牌である![]()
![]()
![]() を用いた役です。
を用いた役です。
和了例)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (役牌=1飜)
(役牌=1飜)
上図のように三元牌で刻子(同じ牌3枚)をつくれば「役牌」という役をつくることができます。また、三元牌以外にも役牌になる牌があります。
場風牌
場風牌とは東場なら![]() 、南場なら
、南場なら![]() です。場風牌も役牌に含まれます。
です。場風牌も役牌に含まれます。
和了例)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (役牌=1飜)
(役牌=1飜)
東場なら![]() が役牌になるため、上図の例も「役牌」で1飜つきます。
が役牌になるため、上図の例も「役牌」で1飜つきます。
自風牌
自風牌は自分が東家なら![]() 、南家なら
、南家なら![]() 、西家なら
、西家なら![]() 、北家なら
、北家なら![]() です。自風牌も役牌に含まれます。
です。自風牌も役牌に含まれます。
和了例)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (役牌=1飜)
(役牌=1飜)
自分が西家だった場合、![]() が役牌になるため、上図の例でも「役牌」の1飜がつきます。
が役牌になるため、上図の例でも「役牌」の1飜がつきます。
まとめ
役牌になる牌は三元牌と場風牌、自風牌がある。
例えば、南場で自分が西家なら役牌は、三元牌である![]()
![]()
![]() と南場の
と南場の![]() 、自風の
、自風の![]() になります。
になります。
平和(ピンフ)
麻雀の基本役で出現頻度も高い平和(ピンフ)について解説します。
平和の和了例
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (平和=1飜)
(平和=1飜)
平和は「3枚1組のグループが4つ+2枚1組の雀頭」という麻雀の基本型です。
平和になるための条件は「3枚1組のグループが全て順子(連続した数字)でないといけない」という条件があり、刻子(同じ牌3枚)が混じってはいけません。
平和になる条件
条件1:全てのグループが順子でなければならない
面子(メンツ)全てが順子(連続した数字)でなければなりません。
条件2:チーをしてはならない
順子でもチーをしてはいけません。平和では門前でなくてはなりません。
条件3:雀頭には役牌を使ってはいけない
平和の雀頭に三元牌や、場風牌、自風牌を使ってはいけません。
条件4:リャンメン待ちでなければならない
テンパイをして当たり牌を待つ際に、リャンメン待ちでなければなりません。
まとめ
条件が多い平和ですが確率の問題からかなり登場頻度が高い役なので、絶対に覚えておきたい役です。
平和はよくタンヤオなどの他の役とも複合します。
タンヤオ
平和と同じくらい登場頻度が高く重要な役にタンヤオがあります。シンプルな役なので覚えやすいと思います。
タンヤオの和了例
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
タンヤオは数牌の1・9牌(老頭牌)と字牌を使わず、2~8までの数牌(中張牌)だけで構成する役です。組み合わせは順子でも刻子でも構いません。また、食い制限がないのでポン、チー、カンをしても1飜のままです。
タンヤオの条件
条件:ヤオチュー牌(1・9牌と字牌)を使わない
タンヤオの条件はヤオチュー牌である1・9牌と字牌を使わないことだけです。あとはアガリの形になっていればアガることができます。
ちなみにヤオチュー牌を使わないことから、ヤオチュー牌を断つという意味で「断ヤオ(タンヤオ)」と呼ばれています。
まとめ
平和と比べても条件がシンプルでわかりやすいと思います。しかし、タンヤオだけでは点数が低いため、よく平和などの役と複合するので、前項で解説した平和とともに合わせて覚えたい役です。
喰い替え・チョンボ・反則行為
ここではよく登場する反則行為などを紹介します。
多牌・少牌
漢字を見るとなんとなくわかると思いますが、何かの手違いで牌が1枚多かったり、少なかったりする状況です。
もし、多牌や少牌になってしまった場合、ペナルティを受けることがあります。このペナルティのことをチョンボといいます。ペナルティー全般のことを「チョンボ」と覚えてしまって問題ありません。
チョンボになった場合
チョンボになってしまった場合、まずはあがり放棄というペナルティーになり、アガることができなくなります。つまり、ひたすらツモ切りを繰り返すことになります。
誤ロン
他にチョンボになる可能性がある反則に誤ロンがあります。自分がテンパイしていないのに「ロン」を宣言してしまった場合や、当たり牌でないのに「ロン」を宣言した場合に適用される場合があります。誤ロンの場合、仲間内でプレイしていた時に牌を倒さない状態(ただロンと言ってしまっただけ)ならばセーフになる場合があり、その場の状況次第といった感じが多いです。
喰い替え
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
上図のような手牌の時に上家(左隣のプレイヤー)が![]() を捨てたとします。その
を捨てたとします。その![]() をチーして
をチーして![]() を捨てるのを喰い替えと呼び、反則になる場合があります。
を捨てるのを喰い替えと呼び、反則になる場合があります。
ルールによっては喰い替えが認められる場合がありますが、基本的には喰い替えは反則である場合が多いので注意が必要です。
麻雀のマナー
麻雀のルールや基本がわかったところで、最後にマナーについて触れたいと思います。
ネット麻雀編
近年、ネットで手軽に麻雀ができるようになったため、ネット上のマナーも度々問題にされることがあるので、みなさんはマナー違反だと思われないように気をつけてください。
ネット麻雀のマナー違反
過度の長考
麻雀をしていて捨て牌に困った場合などに長考することはあるかと思いますが、不用意に長考を繰り返すのはマナー違反に当たる場合があるので注意が必要です。
牛歩
特に悩む状況でもないときに、意図的に捨てるスピードを遅くするものでネット麻雀では「牛歩」と呼ばれ嫌われる傾向にあります。不用意に毎回毎回時間目一杯使うのは牛歩とみなされる場合があります。
ためロン/ためヅモ
ツモあがりや、ロンあがりで当たり牌が出た場合に「ツモ」や「ロン」のボタンをすぐに押さずに、ギリギリまで待ってアガリを宣言するのも嫌われる傾向にあります。
回線切り
自分が負けている、負けそうな状況の時に、意図的にゲームの画面を閉じたり、ネット回線を切ったりする行為はネット麻雀で特に嫌われる行為なのでので、絶対にやらないようにしてください。
リアル麻雀編
仲間内で打つ場合は多めに見て貰える場合がありますが、フリー雀荘などで打つ場合は周りへの配慮が必要です。
リアル麻雀のマナー違反
先ヅモ
相手が牌を捨てる前に自分がツモすること。気持ちが焦ってしまう時もありますが、前の人が河に捨ててからツモをするのがマナーです。
くち三味線/ブラフ
嘘やハッタリなどで、「自分の手はでかいぞ」や「当たり牌は持っている」などと言ったりすること。友達同士ならあまり問題になりませんが、知らない人とやる場合はマナー違反にあたるので注意が必要です。
打ち方の批判
相手がアガった時に「ここはこうした方がよかった」や「そんな安い手でアガるな」などと思う場合があるかもしれませんが、フリー雀荘では初心者も多く来店されるほか、人それぞれ打ち方や考え方があります。絶対に他の方の批判はしないでください。
まとめ
以上で麻雀の基本編は終わりです。麻雀のルールや基本だけでなく、マナーを守って麻雀を楽しんでもらえると私としても嬉しく思います。それでは長文に付き合っていただきありがとうございました。